目次
- 1 ファイアーエムブレムとは
- 2 シリーズ一覧
- 2.1 暗黒竜と光の剣(1990年 FC)
- 2.2 外伝(1992年 FC)
- 2.3 紋章の謎(1994年 SFC)
- 2.4 聖戦の系譜(1996年 SFC)
- 2.5 トラキア776(1999年 SFC)
- 2.6 封印の剣(2002年 GBA)
- 2.7 烈火の剣(2003年 GBA)
- 2.8 聖魔の光石(2004年 GBA)
- 2.9 蒼炎の軌跡(2005年 GC)
- 2.10 暁の女神(2007年 Wii)
- 2.11 新・暗黒竜と光の剣(2008年 DS)
- 2.12 新・紋章の謎(2010年 DS)
- 2.13 覚醒(2012年 3DS)
- 2.14 if(2015年 3DS)
- 2.15 Echoes(2017年 3DS)
- 2.16 風花雪月(2019年 Switch)
- 2.17 エンゲージ(2023年 Switch 予定)
- 3 関連作品
- 4 興味はあるけど、どれから遊べばいいの?
この記事は2019/02/21に書いたものです。
2022/12/30追記
ファ~イアエ~ムブレム♪
て~ごわいシミュレ~ション♪
皆さん。ゲームは好きですか?
私は大好きです!
ゲーム好きの皆さんには新作が出たら必ず買っている思い入れのあるシリーズというのが一つはあるのではないでしょうか。
今回の記事は私がシリーズ買いしている手強いシミュレーション「ファイアーエムブレム」です。
ファイアーエムブレムとは
ファイアーエムブレムとはインテリジェントシステムズ開発、任天堂発売のシミュレーションRPGシリーズ。略称はFE。また、FE愛好家のことをエムブレマーと称する。
初めに断っておくがファイアーエムブレムである。ファイヤーでもエンブレムでもない。
エムブレマーに対するファイヤーエンブレムという言葉はウルトラファンに対するウルトラマンセブンに匹敵する暴言なので注意されたし。
まぁ、実際に発音するときは公式でもファイヤーエンブレムって言ってるんだけどね。
シリーズ最大の特徴はなんと言っても味方ユニットのロスト。
大抵のシミュレーションゲームでは仮にユニットを失っても作り直しできたり、修理費のペナルティがあるだけで次のマップでは復活してたりするものだが、今作においては一度やられたユニットは二度と使う事が出来なくなる。
更にユニット達には容姿や性格などの個性が設定されており、ロストの際には遺言を残して逝くなどただの「駒」ではない為。ゲーム攻略の面でもプレイヤーの心情の面でも味方のロストは重い物を残していく。
この仕様に加え、絶妙に調整されたゲームバランスによって「手強いシミュレーション」として名を馳せている。
同時にシミュレーションゲームのユニットに個性を付ける事によってシミュレーションゲームにストーリー性を持たせることに成功し「シミュレーションRPG」というジャンルを確立させた作品でもある。
とはいえ、近年においてはこの仕様ではコアゲーマーにしか受けないと考えられたのかロストした味方が次のマップには復活する「カジュアルモード」の搭載が一般的になっている他、ロストした味方がその場で復活する「フェニックスモード」というものまで登場した。従来の形式は「クラシックモード」として残されている。初心者はカジュアルから始めて慣れていくといいだろう。
???「クロム君!男は黙ってクラシックモード!!」
シリーズ一覧
暗黒竜と光の剣(1990年 FC)

記念すべき第1作。スマブラでも有名なマルスが主人公。
この頃から基本的なシステムは完成しており味方のロストや赤と緑の騎士、ペガサス三姉妹、お助けキャラの老騎士、寝返り系剣士など後の作品のテンプレを多く作った。
外伝(1992年 FC)

第2作。世界観を前作と共有しているので前作のキャラクターが一部登場している。がストーリー的な繋がりは薄いので前作をやっていなくても問題はない。
二作目にして大きくシステムを変化させており自由に育成が繰り返せるフリーマップ、複数の主人公によって進むストーリー、2段階のクラスチェンジなどの搭載でかなりの異色作となった。
クラスチェンジを繰り返す事で永久に育成出来る魔戦士ループも話題になった。
紋章の謎(1994年 SFC)

ここからハードがスーファミに移行。
本作は二部構成になっており暗黒竜と光の剣をリメイクした第一部とその後日談としてマルスの新たな戦いを描いた第二部の構成になっている。両方共それだけで一本のゲームにできる程のボリュームを誇るので一本で二つのゲームが楽しめると言える。
ただし、容量の問題で第一部はリメイク元から削られたステージ、キャラクターが存在する。これによって一躍ネタキャラとして名を馳せてしまったキャラクターもいる。
聖戦の系譜(1996年 SFC)

執筆者が初めてプレイしたFE。
前作までと世界観を一新し、主人公シグルドとその息子セリス親子二代に渡る壮大な物語が展開される。
異性のユニット同士を自分の好きな組み合わせで恋人にする事が出来、親世代のカップルから生まれた子供が子世代のユニットとして登場する恋愛システムが特徴。子供は親の能力や特徴、武器を受け継ぐ他、カップルになった場合のみ見れるイベントなども多数存在する為、発売から20年以上経った今でも攻略面、シナリオ面両方でカップリング談義が絶えない。
また、シリーズお馴染みの武器の3すくみ、魔法の3すくみもここから登場した。
スマブラにセリスを参戦させるんだよ。あくしろよ。
トラキア776(1999年 SFC)
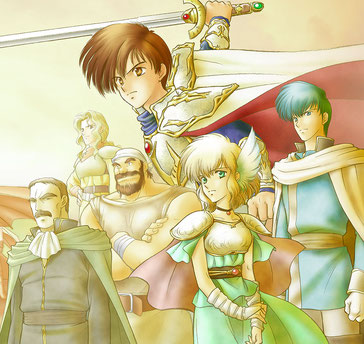
ニンテンドーパワーの書き換え用ソフトとして登場した作品。2000年にパッケージ販売もされた。が、この頃にはスーファミからニンテンドウ64に移行していた為、パッケージ版はあまり流通しておらず現在ではプレミア価格となっている。
前作聖戦の系譜のスピンオフ作品であり聖戦の系譜主人公セリスのいとこである王子リーフの物語を描く。前作キャラも複数登場したり、前作キャラに関係ある人物が登場したりと聖戦の系譜の掘り下げもされている。
独特かつ複雑なシステムを持ち、現在でもシリーズ最高難易度と呼ばれている。
封印の剣(2002年 GBA)

執筆者が最も思い入れのあるFE。
シリーズ初の携帯機。スマブラにも参戦しているロイが主人公。
トラキア776で複雑になりすぎたシステムをシンプルに再構成。更に今作からチュートリアルが実装されたので新規の人でも遊びやすくなった。
また、本編では語られないキャラクターの一面を見れる支援会話システムや上級者向けのハードモードなどが初登場。近年のFEの基礎を築いた作品と言える。
烈火の剣(2003年 GBA)

執筆者的シリーズ最高傑作。
前作封印の剣の20年前を舞台としたスピンオフ作品。
国家間の戦争を描いてきたシリーズにおいて唯一国家間戦争が発生しない作品で、外伝以来となる複数主人公による物語が描かれる。中でも今までのFE主人公のイメージを打ち砕くイケイケ系主人公ヘクトルは人気を博しその後の主人公像に大きく影響を与えた。
封印の剣で荒削りだった部分を調整してより遊びやすくなった他、支援会話の状況によって後日談が変化するペアエンドが実装された。
スマブラにヘクトルを参戦させ(ry
聖魔の光石(2004年 GBA)

前作までと世界観を一新。双子の兄妹エフラムとエイリークの戦いを描く。
中盤でエフラムとエイリークが別行動をとるのでどちらの物語を見るかのルート分岐が存在。両方のルートを見る事で物語の全てを見る事ができる。
システム面では外伝以来となるフリーマップが復活。これにより好きなだけ育成出来るようになったので初心者にも遊びやすい。
クラスチェンジ先を選択できるクラスチェンジ分岐が初実装された。
スマブラにエフラムをさn(ry
蒼炎の軌跡(2005年 GC)

久々の据え置きハードFE。それに伴いシリーズ初の3Dグラフィックとムービーが用意されムービー中にはシリーズ初のキャラクターのボイスが実装された。
スマブラに参戦しているアイクが主人公。ちなみにシリーズ初の平民主人公である。
聖魔からフリーマップが廃止され昔ながらの限られた育成機会、限られた資源で攻略していく従来のFEに戻った。
今までの兵種とは運用方法が大きく異なる獣人ユニットが初登場。難易度選択はノーマル、ハードに加え更に上をいくマニアックが追加。錬成によって武器の強化ができる様になった(ちなみに今作の錬成にはバグがありバランスブレイカーを量産できる)。
完成度、評価は高いがGCがあまり普及していなかった為にソフトも多くは出回らず現在ではプレミア価格。
暁の女神(2007年 Wii)

蒼炎の軌跡の続編。前作から3年後の世界が舞台。
前作登場キャラはほぼ全て続投し前作で残っていた伏線や語られなかった謎に決着をつける完結編。複数の主人公によるオムニバス形式のストーリーが展開される。
外伝以来となる2段階クラスチェンジが復活した。
新・暗黒竜と光の剣(2008年 DS)

第1作暗黒竜と光の剣のリメイク作品。あくまで第1作のリメイクなので紋章の謎は収録されていない。
紋章の謎でリストラされてしまったキャラ達も全員復活。基本はリメイク元に忠実に作られているがシステムは現代の物に作り変えられている。一部のキャラクターの謎の超強化が話題となった。
キャラの兵種を変更できる兵種変更が初実装。これにより選択するクラスを間違えただろコイツ。と言いたくなるキャラにも活躍の可能性が生まれた。
新・紋章の謎(2010年 DS)
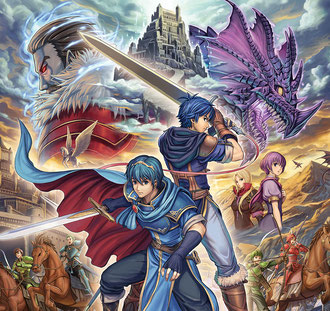
前作に引き続きリメイクされた紋章の謎。原作とは違い暗黒竜と光の剣は収録されておらず第二部のみのリメイクとなった。
現在のFEでお馴染みとなったプレイヤーの分身マイユニットが初登場。カジュアルモードが実装されたのもここから。
覚醒(2012年 3DS)

暁の女神から5年ぶりとなる完全新作。スマブラに参戦しているクロム、ルフレ、ルキナの元ネタ。
元々FEは売上の問題から今作で最後とされていたらしく、紋章の謎から続く世界観に外伝のフリーマップ、封印の支援会話システム、聖戦の恋愛システムと親子2世代の物語、聖魔の分岐クラスチェンジ、蒼炎の錬成、新・暗黒竜の兵種変更とシリーズの様々な要素を集めた集大成となった。
キャラクターボイスに人気声優を多く起用する事で今までシリーズに触れたことのない層にも普及し結果としてシリーズ存続が決定するほどの売り上げを記録した。
if(2015年 3DS)

白夜王国、暗夜王国とシリーズ初のバージョン商法が採用された作品。スマブラに参戦しているカムイが主人公。
バージョンによって敵味方が逆転するため仲間になるユニットやストーリーが大きく異なるだけでなくゲーム内容も大きく変わる。白夜はフリーマップの実装によって自由育成ができる前作から始めたプレイヤーや初めてシリーズに触れる新規勢向け。暗夜はフリーマップがなく育成機会が限られている上に容赦の無いバランスになっているので手強いシミュレーションを求める層向け。
後にDLCで第3の物語「インビジブルキングダム」が配信された。こちらはフリーマップがあるので暗夜よりは楽。
Echoes(2017年 3DS)

第2作である外伝のリメイク作品。
新・暗黒竜、新・紋章の2作品は現代のシステムにリメイクされたのに対して、こちらは原作のシステムを忠実に再現。バランスブレイカーな魔戦士ループまでそのまま移植されている。そこに支援会話システムや新キャラを追加する事で物語やキャラクターをより掘り下げたリメイクとなった。
元々異色作だった外伝を忠実に再現した為にこちらもかなりの異色作となっておりSFC以降からシリーズに触れたプレイヤーは戸惑う事間違いなしである。
ちなみにシリーズ初のフルボイス作品である。
風花雪月(2019年 Switch)

スマブラに参戦しているベレト、ベレスの元ネタ。
据え置きハードとしては暁の女神以来12年ぶりとなった作品。
シリーズ初の学園モノで主人公は学園の教師として教え子たちを導いていく。
学園モノということで授業や放課後の交流などの戦闘マップ以外のオフの姿を掘り下げた物となっており、従来シリーズに比べると穏やかな雰囲気を持つ。
が、それは第一部だけの話であり、第二部になると国家間戦争が勃発。級友たちは国ごとに分かれ無惨な殺し合いを演じることになる。
エンゲージ(2023年 Switch 予定)

2023年1月20日に発売予定の新作。
エンゲージシステムによって過去作キャラクターたちのゲスト参戦が行われる模様。
関連作品
アカネイア戦記(1997年 SFC)
知る人ぞ知るスーファミのマイナー周辺機器「サテラビュー」にて配信されていた作品。当然、現在ではプレイ不可能であるが新・紋章に内容の一部が収録されている。
これをやったことある人は相当なエムブレマーではないだろうか。
幻影異聞録♯FE(WiiU 2015年)
女神転生で知られるアトラスとのコラボ作品。ジャンルはRPG。当初は女神転生とFEのコラボと発表されていたが色々あってアトラスとFEのコラボという形に落ち着いた。
その結果、第一報のPVがとんでもないPV詐欺になってしまっている。
TCGファイアーエムブレム0(サイファ)(TCG 2015年~2020年)
2015年から展開されていたトレーディングカードゲーム。
現在では完全に終了したが近年参入のカードゲームにしては5年とそこそこ続いた。
ファイアーエムブレム無双(2017年 Switch 3DS)
Koeiの人気作無双シリーズとのコラボ作品。任天堂の作品としてはゼルダ無双に続き2回目のコラボとなる。
基本は無双だが3すくみや味方のロストなどFEを意識した要素も多い。
作品の枠を超えたクロスオーバーも魅力。
2022年には風花雪月を原作とした第二弾「ファイアーエムブレム無双 風花雪月」が発売された。
ヒーローズ(2017年 Android iOS)
シリーズ初のソーシャルゲーム作品にして、任天堂初のソーシャルゲーム(スマートデバイス向けゲームはスーパーマリオランが初作品だがこちらは買い切り式でありソーシャルゲームではない)。
各シリーズから様々なキャラクターが参戦しており正にオールスター作品である。
基本無料なので気になるならやってみてはいかがだろうか。ちなみに執筆者はソシャゲは某空の旅で燃え尽きたのでやる気が起きない。
大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ
「DX」でマルスとロイが参戦したのを皮切りに「X」でアイク。「for」でルフレ、ルキナ、カムイ。「SP」でクロムと着実に参戦キャラが増えている。「SP」のDLCではベレト、ベレスが参戦した。
プレイアブルキャラ以外にもアシストフィギュアとして多数参戦している。
ちなみに封印の剣の開発が遅れた事でロイはスマブラDXが初登場作品となった。この時は開発中だったのでキャラが纏まって無かったのか本編とスマブラのロイは性格が異なる。本編のロイは「イィィヤッ!」とか言わないし、別作品の同名キャラをマグマに叩き落としてガッツポーズしたりしない。
project X zone2
3DSで発売されたセガ、バンダイナムコ、カプコンのクロスオーバーゲーム。
ハードが3DSだったので任天堂からのゲスト枠として覚醒のクロムとルキナが参戦している。
セガが誇る遊びの道を極めた伝説の男は何故かクラシックモードのことを知っていた。
興味はあるけど、どれから遊べばいいの?
現状ではひとまず風花雪月をやっておけば問題はない。
未だにGBAやGBAが遊べるDS、あるいはVCが遊べるWiiUを所持しているなら封印の剣、烈火の剣、聖魔の光石のGBA三部作もオススメ。
中でも烈火の剣はチュートリアルの充実とシリーズの中では遊びやすい難易度となっているので入門用に最適。遊びやすい難易度に慣れたらシリーズ屈指の難易度を誇る「ヘクトル編ハード」もあるので入門から腕試しまで烈火一本で出来る。
他二作も入門用にオススメできるが封印はチュートリアルが本編中に無く烈火に比べるとテンポが悪い部分がある事(烈火が封印をブラッシュアップした作品だから当たり前なのだが)、聖魔は育成が簡単な上に難易度がかなり低めになっている(とは言っても初心者には普通に手強いと思うが)ので烈火よりもFE特有の緊張感が味わいにくい事が強いて言うなら難点だろう。
ただ、GBA三部作はどれも出来が良いのでここから始めることをお勧めしたい。
当然それ以外の作品が悪いと言うことはない元祖主人公マルスの物語を描いた紋章の謎や今なお語り継がれる高いドラマ性を持った聖戦の系譜なども今ならVCやNintendoSwitchOnlineで手軽に遊ぶことができる。
一方で入門編として絶対にオススメされないのがトラキア776。前述の通り複雑すぎるシステムに加えチュートリアルが全くない為システム理解に戸惑う事と難易度もかなり高く戦略を求められる為、初心者にはオススメできない。熟練のエムブレマーにはこの戦略性の高さに惹かれる者も多数いるが初心者は別の作品で経験を積んだ後に腕試しとして挑戦してみてほしい。